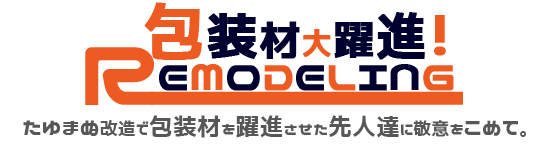食品包装のはしりは缶詰
食品の包装材としてまず挙げなくてはいけないのが缶詰と言われており、現代では飲料用含め幅広く使われていることからも、その優秀性が認められている証といえるのではないでしょうか。
缶詰の始まりは、西洋において軍人の携行食用に考えられたものとされ、外気の影響を受けず被包装材を保護する優れた方法として、特許が取られるなど一気に広まっていったと言われています。
金属缶という包装材は、加熱や冷却を可能とすることから今でいう食品加工技術のはしりともなるもので、先行していた瓶詰と違い軽く割れないというメリットも普及のきっかけともなったと言われています。
さらに、金属缶はいまでは資源再利用の代表ともされ、リサイクル可能なことから原材料の安定供給も確保されるほか、印刷技術の進歩で消費者にアピールする商品としても優れたものとなっています。